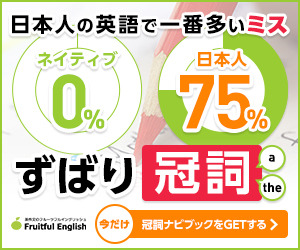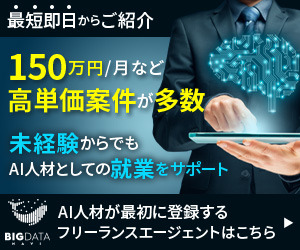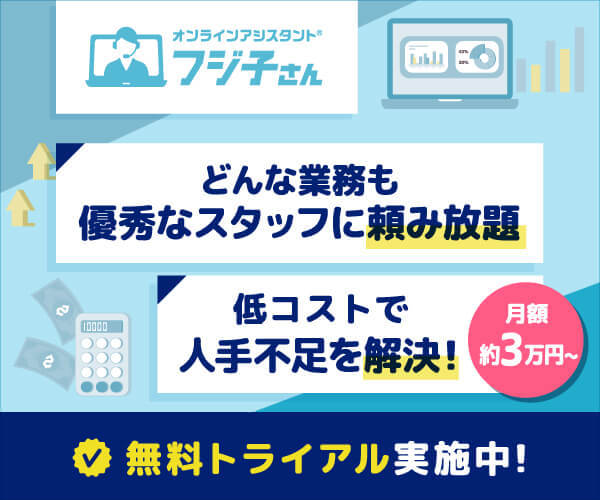・ゲーム産業では生成系AIが以前から意識されており、ゲーム制作にも導入されてきた。
・AIによる作品生成は一定のクオリティーを持つが、人間のアーティストがブラッシュアップしてクオリティーを高める作業が重要。
・AIの使いこなしには専門のエンジニアの育成だけでなく、コードを書かないゲームデザイナーやプランナー向けのAIツールの開発も重要。
「高度なAIが出てきても、人間に取って代わることはない」80点のものを100点にできるのは人間だけ…研究者が語った「AIとの正しい付き合い方」https://t.co/YNGij7TT3M
— 黒井五郎(News U.S.) (@goro_newsus) May 25, 2023

この記事では、ゲームAI開発者の三宅陽一郎氏のインタビューが紹介されています。三宅氏は、AIの進化によって人間の創作活動が無価値になるのではないかという懸念について話しています。
三宅氏は、ゲーム産業では以前から生成系AIに関心があり、1980年代からプロシージャル・コンテンツ・ジェネレーション(PCG)という技術を使ってゲームを作り出す取り組みが行われてきたことを説明しています。また、最近ではAIによる絵画や音楽の生成が話題になっており、AIがゲーム制作にも導入される可能性についても触れています。
三宅氏は、AIによって生成された作品については一定のクオリティーがあると認めつつも、ゲーム制作においては人間のアーティストがAIが作ったものをブラッシュアップし、さらにクオリティーを高めていく作業が重要だと主張しています。彼は、「80点のものを100点にする」作業は人間の仕事であり、AIと人間の共同作業が一般化すると考えています。
また、三宅氏はAIを使いこなすためには専門のエンジニアの育成だけでなく、コードを書かないゲームデザイナーやプランナーでも使えるようなAIツールの開発が重要だと指摘しています。
総じて言えば、三宅氏はAIの進化が人間の創作活動を補完し、よりクリエイティブな作業に集中することを可能にすると考えており、AIと人間の協力が重要だと主張しています。
コメント欄の意見:
palさん:AIを活用した顧客個別対応やサービス計画は効果的であり、ゲーム業界も異業種人材との創発が鍵になるだろう。
bさん:80点の結果を50のコストで出すAIと、100点の結果を100のコストで出す人間のどちらが良いか考える必要がある。ただ、ホワイトカラー系の仕事が減るのは心配だ。
kubさん:AIは人間の仕事を効率化し、人間はクリエイティブな作業に集中できるようになる。人間の生活は豊かになるだろう。
asdさん:AIは人間の速度や多様性を超えており、特定の分野では人間を凌駕している。AIの利点である並列化と機能拡張は生物の能力を遥かに超えている。
bucさん:現時点ではAIの成果が平均的な人間の成果を上回っており、将棋やチェスのようなタスクではトッププロですら勝てなくなっている。
北極星さん:80点のものばかりが売れる社会ではなく、値段や運用性、入手性に重点を置く商品も存在する。地域に存在する商品の方が有り難がられる。
ヴァ二ラ・アイスさん:AIになりたいと憧れる子どもはいないが、AIを開発する人になりたいという子はいる。人は人に憧れて人になっていくのかもしれない。
taiさん:欧米のゲーム会社は異業種との結びつきを重視し、大きな投資をしている一方、和サードは投資や研究に無理な相談だったかもしれない。
yvtさん:AIは形を作る真似事はできるが、人間の感性に訴えることはまだできていない。イラストレーターの仕事はなくならないだろう。
hp-city.com:さんIT系では既に平均的な専門家を越えているAIが存在し、一般的なシステム開発エンジニアの仕事がなくなるのは時間の問題かもしれない。